| このホームページを見て自分で修理する人に注意・アドバイス |
当方よりのご注意
- このHP(HomePage)は、御自分で機器修理の参考にする為、製作しておりません。
このHPは、一般のユーザーが、安心し、納得して修理依頼が出来る事を目的に、製作して有ります。
当方は、商売で行っておりますので、HPに乗せた修理内容が全てでは、有りません。
当然の事ですが、ここがポイント等の場所は、隠して有ります。
- 御自分で機器を修理する為の質問は、全て有料です。
修理の為の技術的質問・資料(回路図、サービスマニアル)は全て有料です。 又、提供しない場合あります。
- 修理する為の部品は、原則お売り出来ません。
修理する為の部品は大量・先行購入して有りますが、当方は「部品屋」では有りませんので、原則、お売り出来ません。
|
当方の修理の考え方&アドバイス
- 機器修理の為に回路図や、サービスマニアルが必要と良く言うが、これは間違い。
回路図が無ければ修理出来ないは、言い訳です。
本人の技術レベルが低いのが原因。
但し、商売となると、競争の世界。
利益優先となり、話は別です。
回路図等の資料があると、修理時間が早くなり(=修理費が安くなります)必須となります。
よって、修理作業は単純作業の繰り返しで、小生は面白く無く、新しい発見の驚きもありません。
- 修理機器に対面している時は、回路図が頭の中に有ること。
普通の人は、2つの仕事を同時にするとミスを起こし易く、十分な思考が働かない。
事前に回路図を十分に理解し、頭の中に入れてから、機器に向かう事。
当方は、修理途中に撮影をするので、必須となります。
- 壁に当たった時は、時間を掛ける。
解らなくなったら、休み、体調を整え、何回も・何回も挑戦すること。
「継続は力なり」と言う通り、努力こそが、天才に追い付き、追い越す道。
自分の力を信じ、未来を確信し、頑張って行くのです。
厳冬を耐えれば、やがて、春が来ます。
日が昇る前が1番寒く、そして最も暗いのです。
寒さが厳しければ、厳しいほど、暗ければ暗いほど、ご来光が身にしみます。
頑張ろう、自分の力を信じ、未来を確信し.........
- 解らないことは、自分で調べ、人に聴かない。
目の前の山は、必ず自力で乗り越える事。
人の力を借りて乗り越えると、次の山も、又、自力で乗り越えれれない。
これでは、何時になっても、自力で乗り越えられず、問題解決能力が形成されない。
この能力を養うのに最適なのが、コンピューターの「プログラム言語」、その製品が自分の脳みそ、その働き。
デバッガーに怒られると、コンピュータに八つ当たりする、それを黙って受け止めるコンピューターは偉い。
しかし悪いのは何時も自分なり・・・
C言語、VisualBasicのファンクションコールが自在に使えればOKでは。
- 測定機器が無いと修理出来ない。
これも、1.番の「回路図が無ければ修理出来ない」と類似している。
過日、大手の恵まれた設計ベンチにいた者に、修理をさせたら、あれが欲しい、これが無ければ出来ないの連発。
無いのは、お前の頭の中の知識、と一喝で終わり。
裕福な東大卒両親で、兄弟も東大入学の家族の1人が東大に合格しても、本人の喜びもそこそこ、周りも騒が無い。
何もかも揃っていれば、出来て当たり前、合格して当たり前、喜びも、感動も起きません。
|
小生のお薦めの技術・技能収得方法
- キットを製作する場合
A.作る前に回路は頭に入れる=暗記する=回路が自分で書ける事。
B.完成したら、全部バラスし、再度組み立てる。壊した部品は適宜補充する。
C.プリント基板を使用している場合、全ての部品配置を考慮し、基板を製作する。
D.使用している部品の規格・性能を熟知し、上位部品が無いか調べる、更に回路の変更を考える。
E.入手出来る最良の部品を使用し、再度、組み立てる。
- 古い機器をいじる方法
A.自分のレベルに合った、同じ機器を2台以上用意する。1台は完動品が良い。
選定する機器は、大手メーカーの大量に売れた後期生産品が良い。
理由は回路設計・部品配置・基板設計の完成度が高く非常に参考になる。
B.回路図を入手する。
但し、勉強の為には、サービス・マニアルは不要。
C.回路図を頭に入れる。
少なくとも、これから修理する部分は覚える。
D.必ず「PLAN・DO・SEE」の行動をする事。
回路図を読解し、現状の症状を考え、ここが悪いと決断して、修理し、結果をみて再考する。以下繰り返し。
これ無くして、又は人の真似をして、修理成功しても、自分の力にならない。
E.交換する部品は、1個ずつ交換し、様子を見る。
但し、自信が無い場合、元に戻さない方が良い。
理由は関係している場合がある為。
F.修理するだけだと、2台を比較して見つける方法が、有る。
修理は早いが、勉強にはならない。
G.悪い所が見つかり、修理完了したら、何故壊れたか原因を考える。
H.そして、原因を取り除く。
無論、回路・部品の変更はついてまわる。
I.必ず記録を残す。学生と違い、社会人は、作業の間が開くので、必修です。
- 技術(知識)・技能は両輪です
A.結構両方が、助け合うものです。
B.基板から部品取りをするだけでも、半田付けの技能が向上します。
当然、「半田吸い取り器」、「吸い取り網線」も使わないで、外す事。
C.回路を理解するのは、時間がかかるです。
この時、回路図を起こすのが良い。
そうすると、「基板の部品配置」から「回路図」が浮かび、 「回路図」から「基板の部品配置」が見えるのです。
D.無線機器の「PLL回路」、オーディオアンプの「多段差動増幅回路」の理解には、十分な期間が必要でしょう。
- 測定機器・道具
A.測定機器は最低限で良い。
B.工具も最低で良い、其処に工夫が生まれる。
C.小生が、そろえているのは、商売だからです。 ある意味ハッタリです。
人に見せる測定機器と、自分で使い良い測定機器は異なります。
- 目標とするお薦め機器
A.無線機器では、TRIOの「TS-820/830のPLL回路」、 バンドごとに独立しているので理解しやすい。
送信機より受信機の方が一見易しいですが、SINADのレベルになると受信機が難しいです。
これ以後の機器は、周波数が広くなり難しいです。
B.手始めはSONYのアンプが完成度が高くお勧めです。
そして、「sansuiのAU-D907X」が解れば、後は慣れでスイスイ行けます。
メインAMPの方がプリAMPより易しいです、プリAMPはレベルが低く難しいです。
レコードプレヤはさらにレベルが上がります。
C.真空管製品は、感電事故に注意です。
感電その物より、感電の衝撃で、物を落としたりする為の事故が被害甚大です。
- 大凡の収得期間(小生の独断と偏見)
A.工学部電気系卒業者=2年。
B.他学部卒業者=5年。
C.ハムやオーデオ・マニヤで半田鏝経験者=2年。
本業の仕事が厳しい時期なので、実際にはモットかかるでしょう。
|
最近の自前修理の失敗例
- HMA-9500mkⅡ 13台目 平成15年4月15日到着、2度目9月10日到着。 修理の様子は、こちら
基板を取り外さず、抵抗をカットして交換し修理に挑戦して、途中で依頼される。
後で、電解コンデンサーは自分で交換するので、取りあえず、通常修理(=悪い所のみ修理)で納品。
しかし2回目修理
チューニングを失敗し、何回かのミスでフューズを飛ばす。
モジュール焼損で修理。
- YAMAHA BX-1 平成17年3月27到着。 修理の様子は、こちら
電解コンデンサーを交換、メイン(終段用)電源の大型電解コンデンサーの逆接続。
対策方法。
取り外す前の事前チエックの不十分の為。
基板に極性が印刷されていても、信用せず、自分で全てマークを付ける事する。
又、交換前後を、デジカメで写真を取り確認する。
この様に、2重3重にチエックをする。
- ONKYO M-509 平成17年4月15日到着。 修理の様子は、こちら
電解コンデンサーを交換時、他の部品に力を加えたり、コネクターの抜き差しにより、基板の半田不良を起こした。
運悪く、終段TR(トランジスター)のバイアス回路だったので、終段TR(トランジスター)を焼損し、メインフューズを飛ばす。
さらに、何回もフーズを取り替えて、飛ばしたので、逆流して、前段TR(トランジスター)/FETを焼損する。
対策方法。
回路を理解し、チエックを十分行う事。
- Sansui AU-X11 平成18年10月16日到着。 修理の様子は、こちら
大手計測機器メーカーのサービス員(多分)。基本的に技量不足。
終段TR(トランジスター)焼損し、前段TR(トランジスター)/FETを焼損する。
対策方法
もっと簡単な機器で経験を積むこと、「ローマは1日にしてならず」=「お金も沢山かかります」
- Technics SP-10mkⅢ(SP10mk3) 平成18年10月16日到着。 修理の様子は、こちら
大手計測機器メーカーのサービス員(多分)。基本的に技量不足。
ピッチコントローラーIC「MN6042」不動にする。
対策方法。
静電対策をしっかりする。
全体的に、半田付けの「技能」が劣ります。 これだけは理屈でなく、慣れが必要です。
カバーする1方法は、「温調半田こて」が有りますので、これを使うのが良いかも、でも高いです。
小生も、購入しましたが、慣れが必要ですね?
|
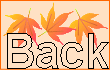  |
ここに掲載された写真は、肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません、よって、写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。
Copyright(C) 2020 Amp Repair Studio All right reserved. |